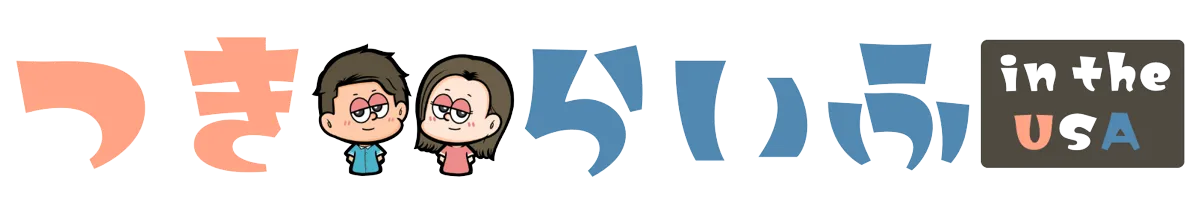【海外赴任準備】退職して帯同するプレ駐妻さんに必要な手続きリスト

こんにちは、アメリカミシガン州で駐在妻をしているつきユカです。
- 帯同を決めたけど、何を準備すればいいかわからない
- 今働いていて忙しいから勘弁して!
- 帰った後のキャリアが心配・・・
というお悩みを解決します。
今、専業主婦の方は、【帯同家族全員共通で必要な準備・手続きリスト】の記事が役立ちます。
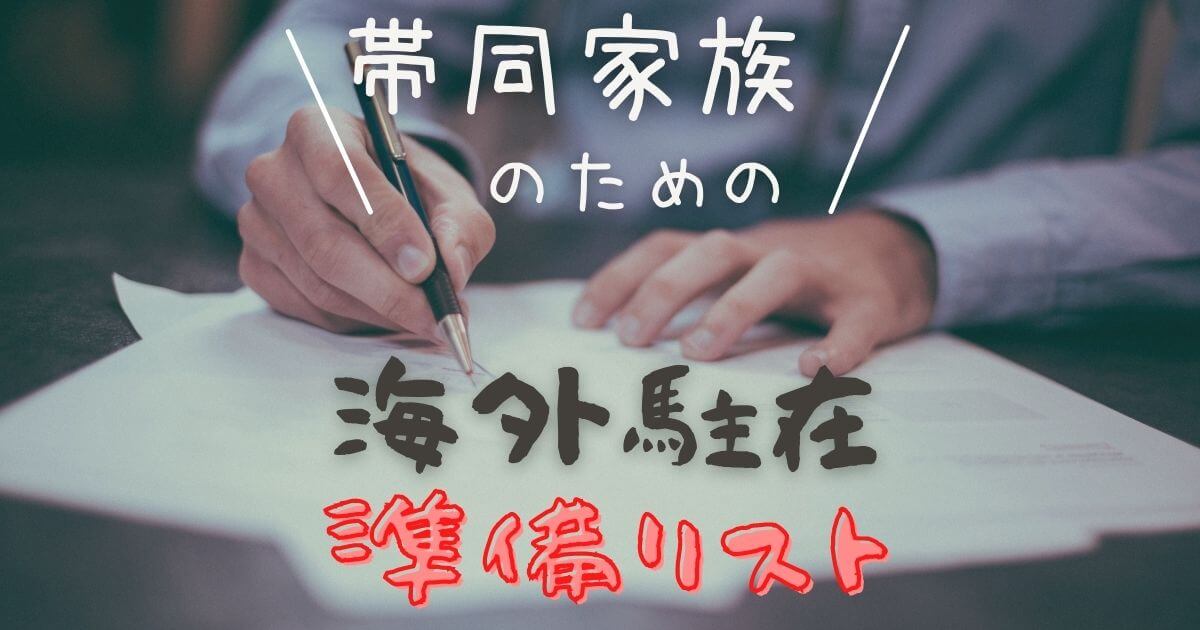
今働いているプレ駐妻さんに必要な手続きリスト

- 退職(休職)時期を決める&手続きをする
- 企業型確定拠出年金→個人型確定拠出年金(iDeCo)への移管手続き
- 健康保険証の返還&扶養家族として加入手続き
- 国民年金の手続き
- 失業保険受給期間延長申請
- 所得税の納税
退職(休職)時期を決める・手続きをする
退職日と最終出社日をいつにするか決めましょう。
私の場合は、4月が山場を越えて落ちつく時期だったので、最終出社日を4月上旬にしました。
(有休消化の後、6月に退社し渡米)
- 最終出社日:最後に勤務する日
- 退職日:会社の所属から離れる日=当日まで社員です
ボーナスや有休がもらえるタイミングなども考慮したいですよね。
あなたは、今まで精一杯会社に貢献してきたので、遠慮する必要はありません!
退職(休職)手続きや復職制度申請など、会社によって異なりますが漏れなく手続きしましょう。
2.企業型確定拠出年金→個人型確定拠出年金(iDeCo)への移管手続き
※そもそもiDeCoって何と思われた方は、こちらのiDeCc公式サイトで確認してください。
ご自身のお金に関する大事なことなので、知らないのは大損する可能性があります。
退職すると企業型拠出年金は退会しなければならないので、今まで貯めたお金を個人型へ移管する手続きが必要です。
会社勤めの際には、毎月掛け金を出していたかと思いますが、海外在住者は禁止されています。
今まで貯めたお金を資金にして、選んだ銘柄に投資します。
新たな掛け金を追加できないところ以外は、今までの企業型確定拠出年金と同じかと思います。
私は楽天証券の「全米株式インデックス・ファンド」という銘柄に惹かれて楽天証券に決めました。
複数社検討されたい方は、早いうちに資料請求されることをおすすめします。
ただ、実際の移管手続きは、退職後にしかできません。
退職後に送付される移管番号を申込書に記載して送付します。
※申込日=退職日翌日の日付にする
また、申込書を郵送した後に承認されて通知が来るまで2カ月程度かかります。(どの証券会社でも同じ)
通知書にログイン時に必要な情報が記載されているので、退職から2ヶ月以内に渡米される場合は、日本のご家族や友人などに代わりに受け取ってもらう必要があります。
健康保険証の返還&扶養家族として加入手続き
ご自身の勤務先の健康保険証は退職日以降使えなくなり、保険組合に返却が必要です。
また、新たに旦那さんの会社の健康保険組合に扶養家族として加入することになります。
加入日は退職日の翌日とします。
手続き上、どちらのカードも手元にないタイミングがありますが、万が一の際には後から保険を請求できるそうなので安心してください。
国民年金の切り替え
国民年金(第1号・2号)に加入している場合は、3号への切り替えが必要です。
これに関しては、夫の会社が健康保険の扶養手続きと一緒にやってくれたので、私は会社に書類を提出するのみでした。
直近の所得を証明するものが必要だったので、過去1年分くらいの給与明細を用意しておきましょう。
ご自身で手続きが必要な場合は、日本年金機構HPをご覧ください。
失業手当受給期間延長申請
失業保険の受給期間は、原則退職日から1年以内ですが、海外勤務に帯同する場合には「最大3年まで延長」できます。
申請は、退職日翌日から30日以内に行わなければなりません。
詳細は、こちらのサイトが非常にわかりやすいです。
ただ、私の場合は赴任期間が5年予定であったこと、夫の会社の扶養条件に失業手当をもらっていないことの記載があったので申請していません。
所得税の納税
所得税は「1月1日~12月31日までの所得」に対して課税されるので、退職後も12月31日までに発生した所得に対しては支払い義務があります。
在籍中は会社が手続きをしてくれていましたが、退職後の数回はご自身で納税が必要です。
私の場合は、6月に退職したので「第1期と2期」は会社が代行してくれ、後半の「第3期と4期」のみ自分で納税が必要でした。
郵送されてくる請求書には、銀行の窓口振込、コンビニ振込、PayPayやLINE Payなどの電子マネーにも対応している旨記載がありました。
ただし上記の電子マネーは海外からの入金には対応していないので、日本にいるご家族に立て替えてもらうしかないです。
アメリカの確定申告に必要な物

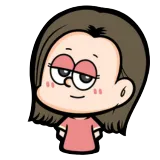 つきユカ
つきユカ私は日本での手続きを終えて、すっかり油断していたのでこちらの記事を追記しました
アメリカでは毎年2月頃に確定申告があり、「配偶者が当年度に他国で働いていた場合」はその所得や納税額を夫の確定申告時に申告しなければなりません。
我が家がもらったオンライン申請書には、源泉徴収票を添付しなければなりませんでした。
退職後1~2ヶ月後に配布される、「源泉徴収票」と「退職所得の源泉徴収票(および特別徴収票)」は電子データで保管しておきましょう。
不安解消法


準備は万全だけれども、現地での生活が不安…
思う方も多いのではないでしょうか?私もそうだったのでよくわかります。
そんなあなたに、おすすめの不安解消法を3つお伝えします。
- SNSで現役駐妻さんと繋がる
- 海外駐在帯同の本を読む
- 駐妻専用の英語を学ぶ
SNSで現役駐妻さんと繋がる


現地の情報をもっと詳しく、最新情報を知りたい場合はSNSが一番手っ取り速いです。
具体的には、TwitterやInstagram、Facebookが良いでしょう。
過去のプライベートな投稿をさらさないために、情報収集専用アカウントを作るとよいです。
この時の注意点があります。
赴任先の近くに住んでいる人の情報を集める
アメリカはとても広いので、都会と田舎、西海岸と東海岸では全然状況が違うからです。
私のInstagramアカウントではアメリカ全土にお住まいの人に役立つ情報を発信しています。
まだ始めたばかりですが、ネタはたくさん持っているので乞うご期待ください!
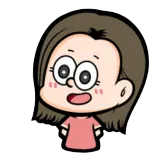
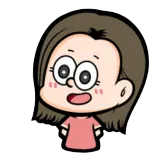
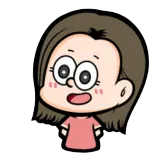
フォローしてくださるととても嬉しいです!(アカウントはコチラ)
2.海外赴任帯同の本を読む
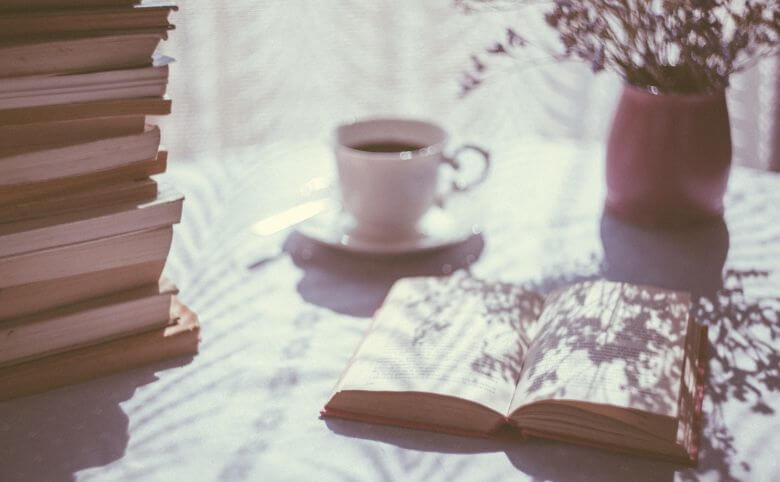
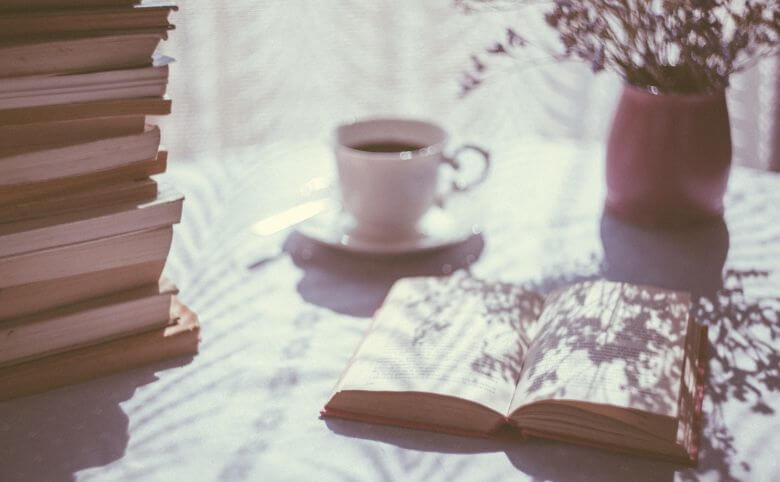
海外に行って何をしたら良いかわからず悩んでいるあなたには、以下の書籍がおすすめです。
ご自身も複数回駐妻を経験された作者が、駐妻経験者にアンケートを実施して「生の声」を集めたもので、充実した海外生活を送るヒントがたくさん詰まっています。
- 語学の準備はどのくらいして渡航したの?
- 現地では何をしていたの?
- 駐妻になってどんなことが身に着いたの?
といった、プレ駐妻さんが気になるポイントがたくさん記載されています。
SNSは便利ですが「駐妻って暇だと思いますが何してるんですか?」とは聞きづらいですよね・・・。
この本はノウハウ本ではないので、正解が書いてあるわけではありません。
しかし、体験談を知ることで「駐妻生活はこんなことに挑戦してみたいな」というぼんやりとした考えが浮かぶかもしれません。
それが大切です!
文字が大きいので、書籍慣れしていない人でも読みやすいです。
私も渡航前にこの本に出会い、不安な気持ちが少し楽になったのを覚えています。
3.駐妻専用の英語を学ぶ
どんな英語も不自由なく話せるようになるのがベストですが、短い準備期間で全部を習得するのは難しいですよね?
そこで、駐妻が出くわす場面に特化した英会話が学べる駐在妻英会話オンライン講座がおすすめです。
- 近所付き合い
- 病院での会話
- ママ友との会話
- 学校の先生との会話
- 購入した商品の返品、交換
- 住居のトラブル
フレーズを身につければ、いざという時にしっかりと自分の意思を伝えられ、お子さんがいる方はお子さんを守ることにも繋がります。
月額3,500円でレッスン受け放題、1レッスン10〜20分でいつでも自分の好きな時に受講できます。
14日間無料でトライアルできるので、気になる方はぜひ受講してみてはいかがでしょうか?
駐妻の英会話だけでなく、いろんな場面で使える総合的な英会話力を身につけたい人は、レッスン回数無制限のネイティブキャンプがオススメです。


引っ越しの手続き
荷物の整理や出国に関して必要な手続きについては、こちらの「帯同家族に必要な手続きリスト」でご紹介しています。
どうぞ合わせてご覧ください。
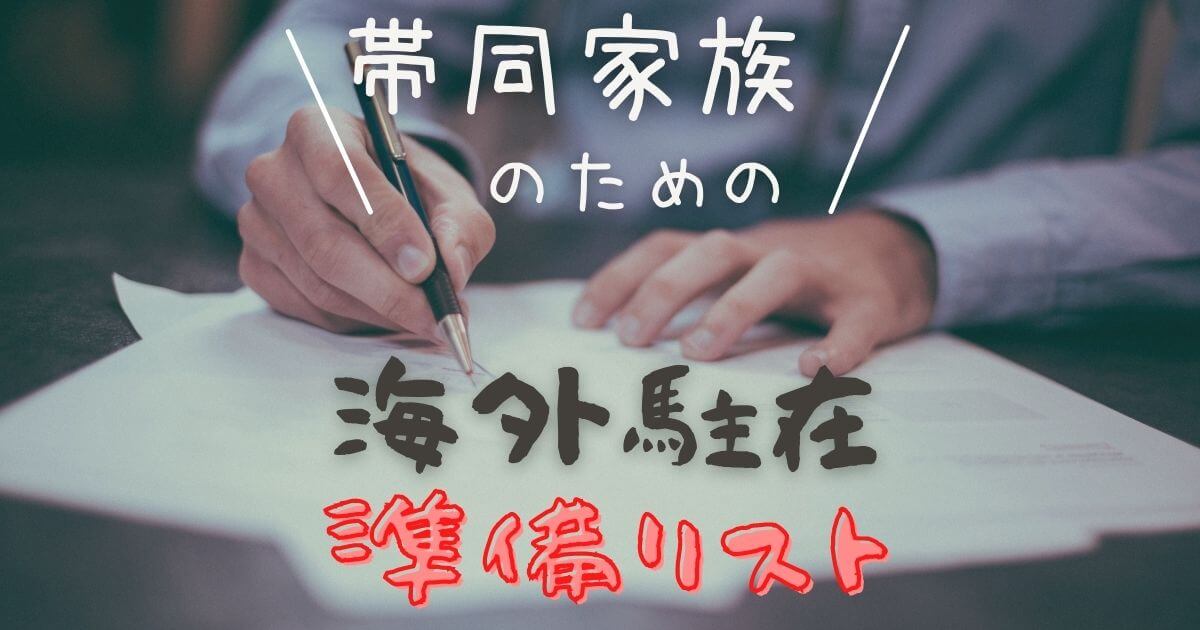
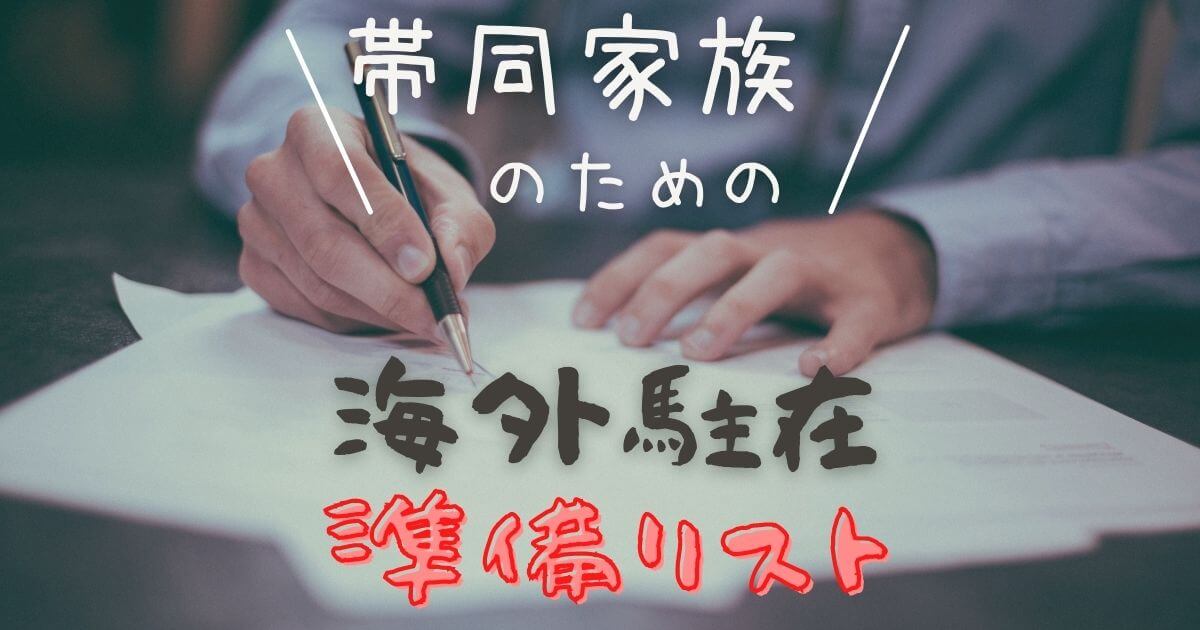
みなさんの渡航準備がスムーズに行くことを祈っています。
それでは、またお会いしましょう! See ya!!